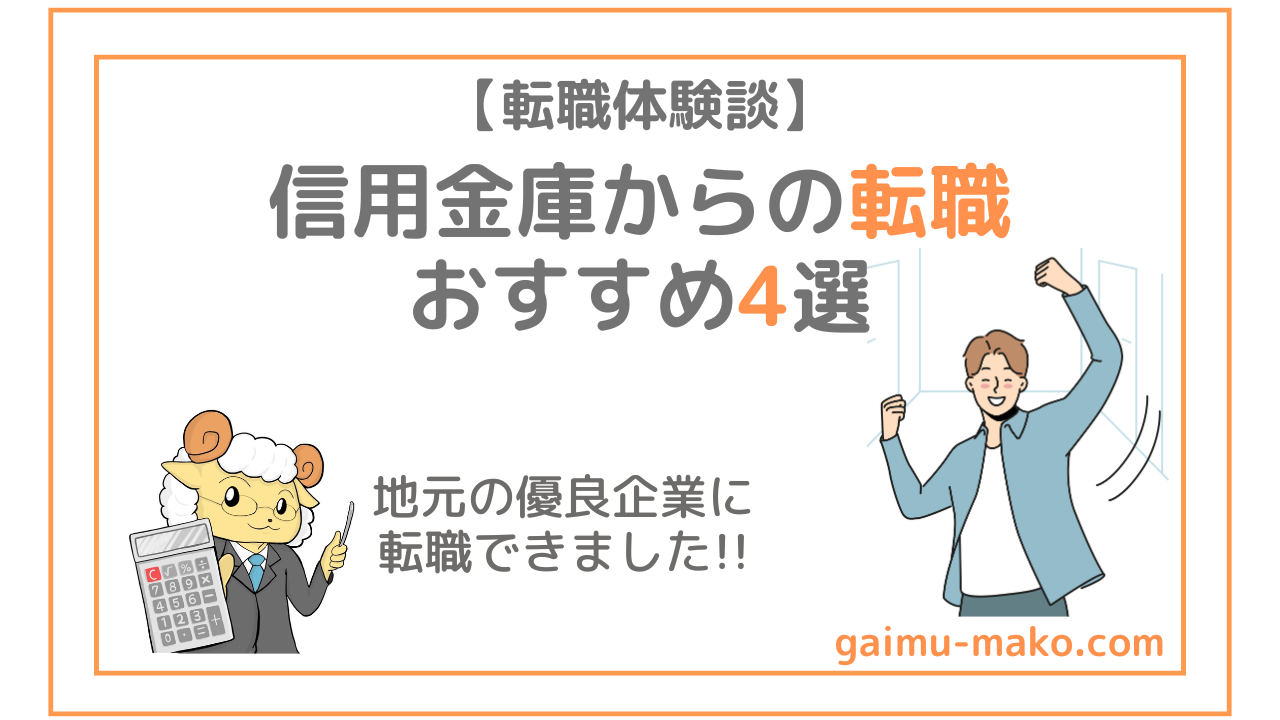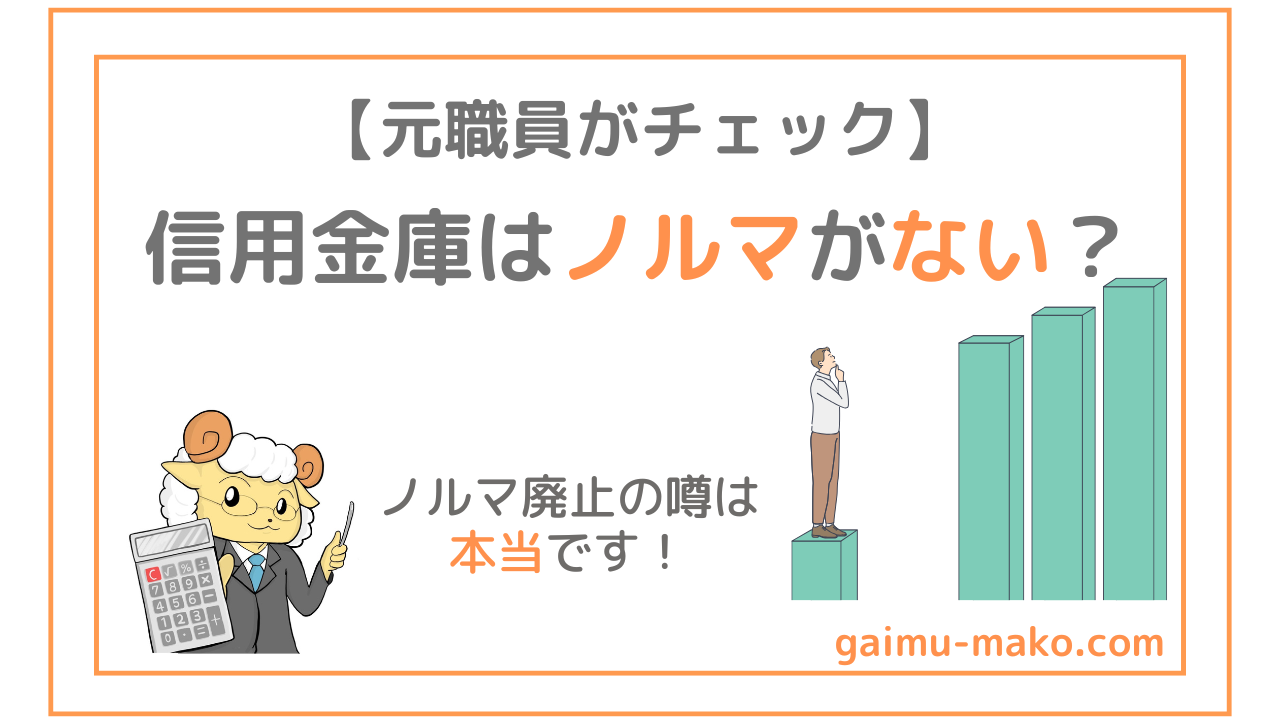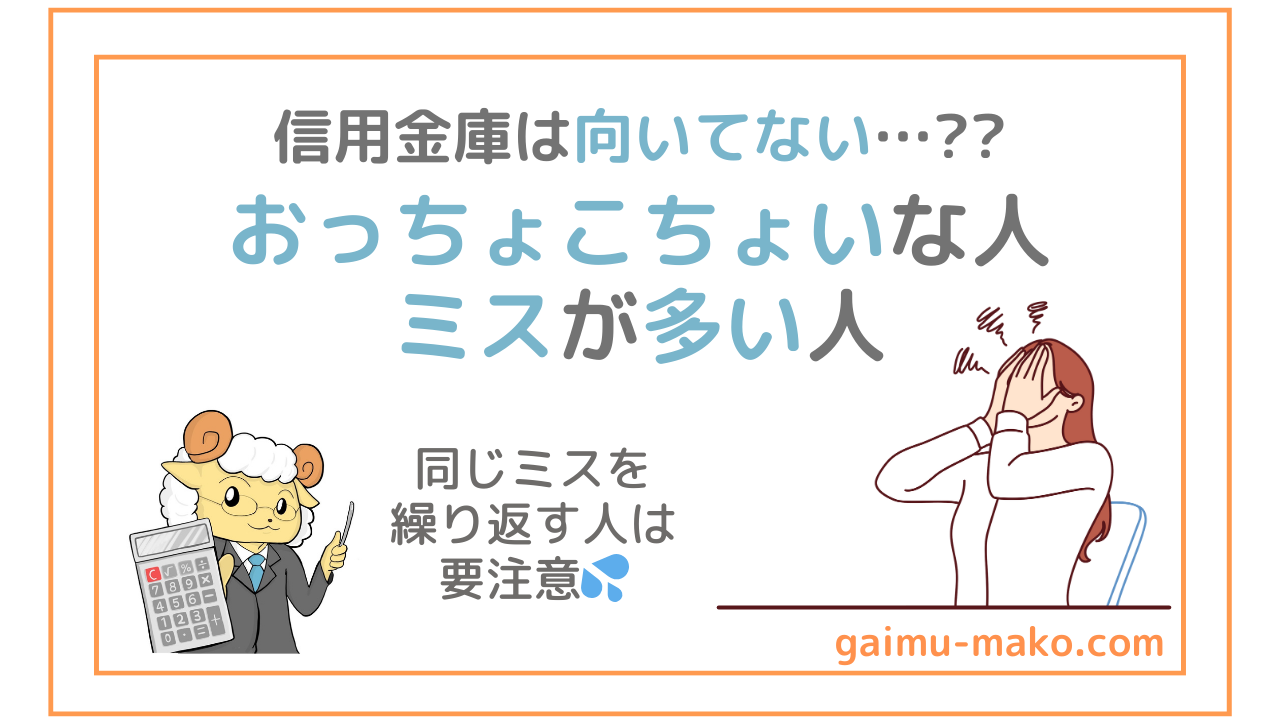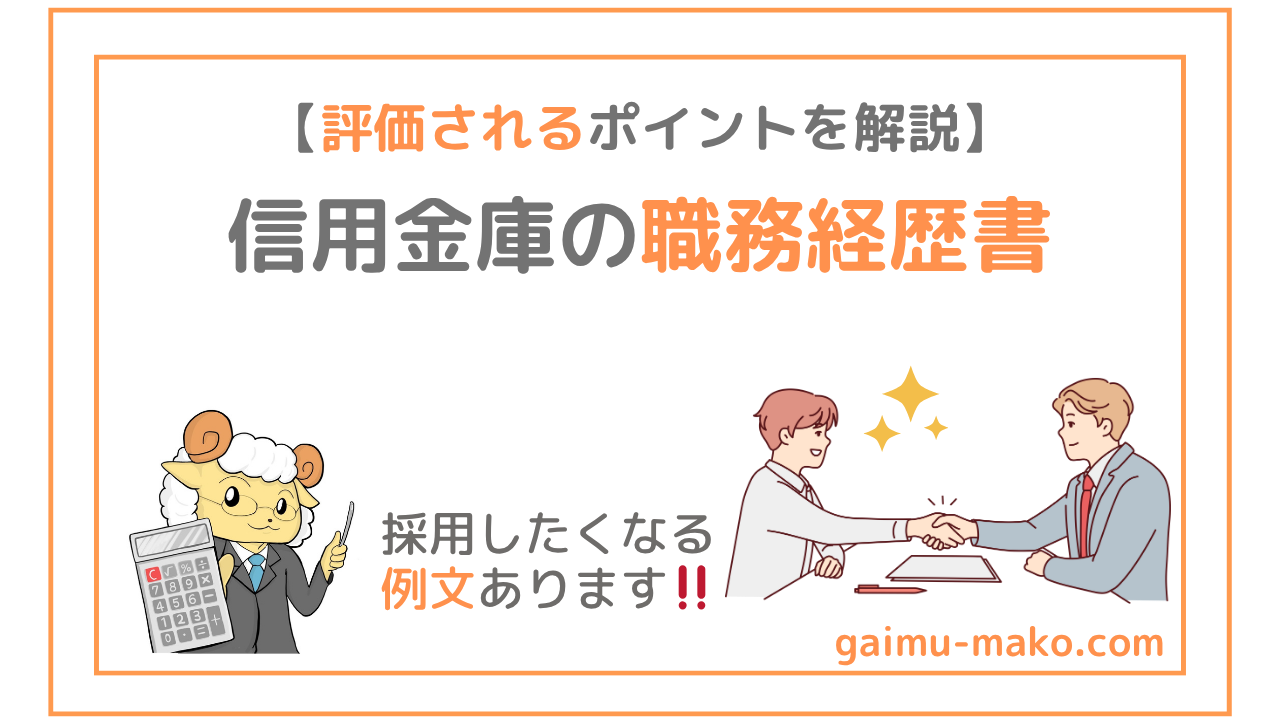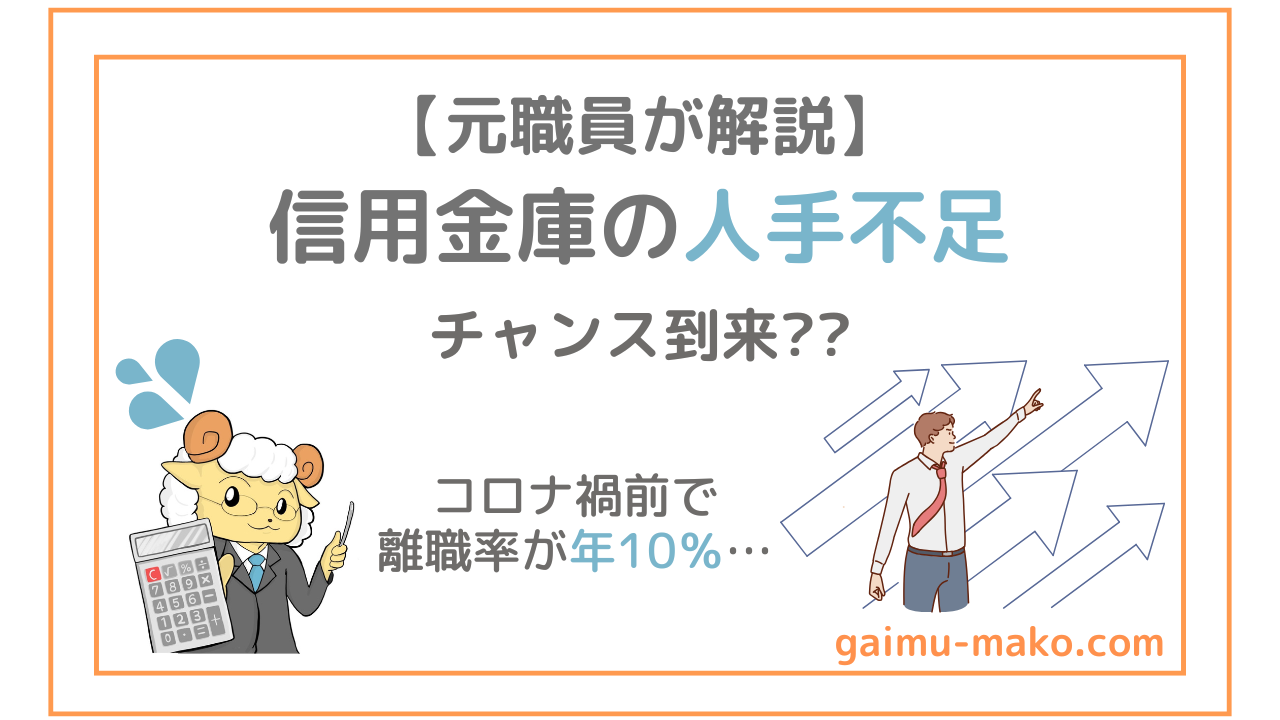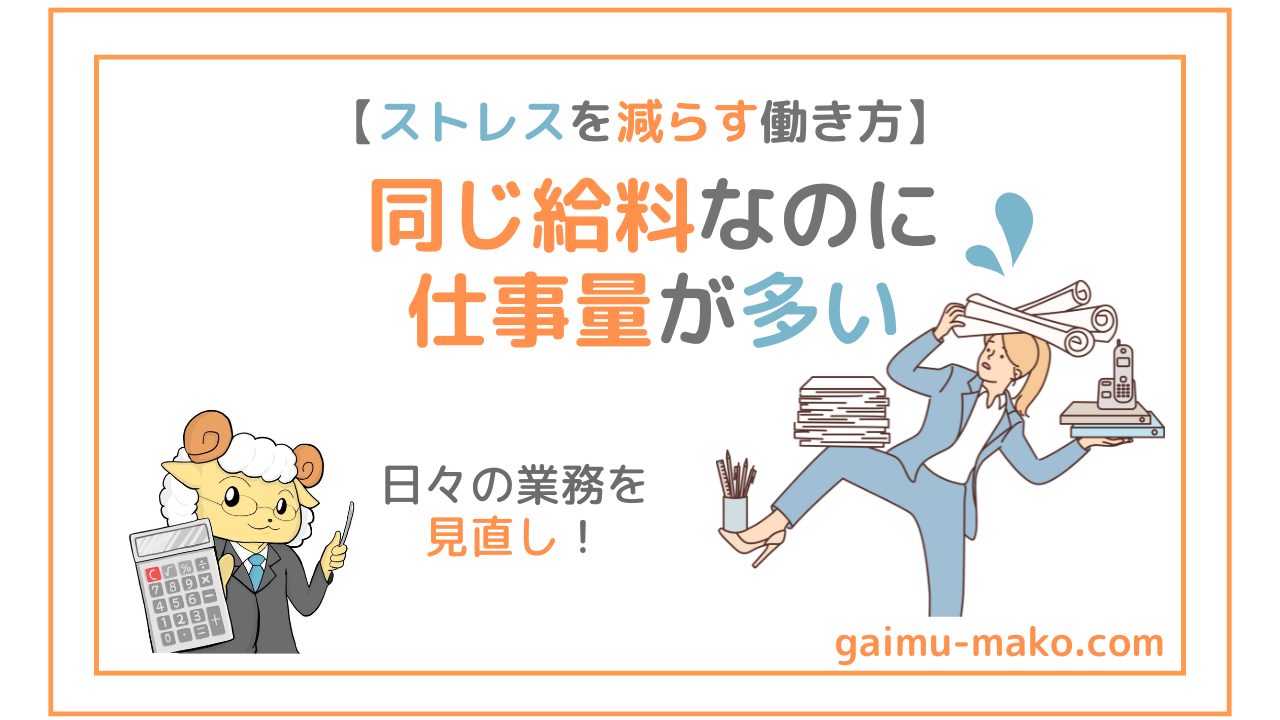信用金庫は将来性ある?今後なくなる?噂の理由を元信用金庫職員が解説
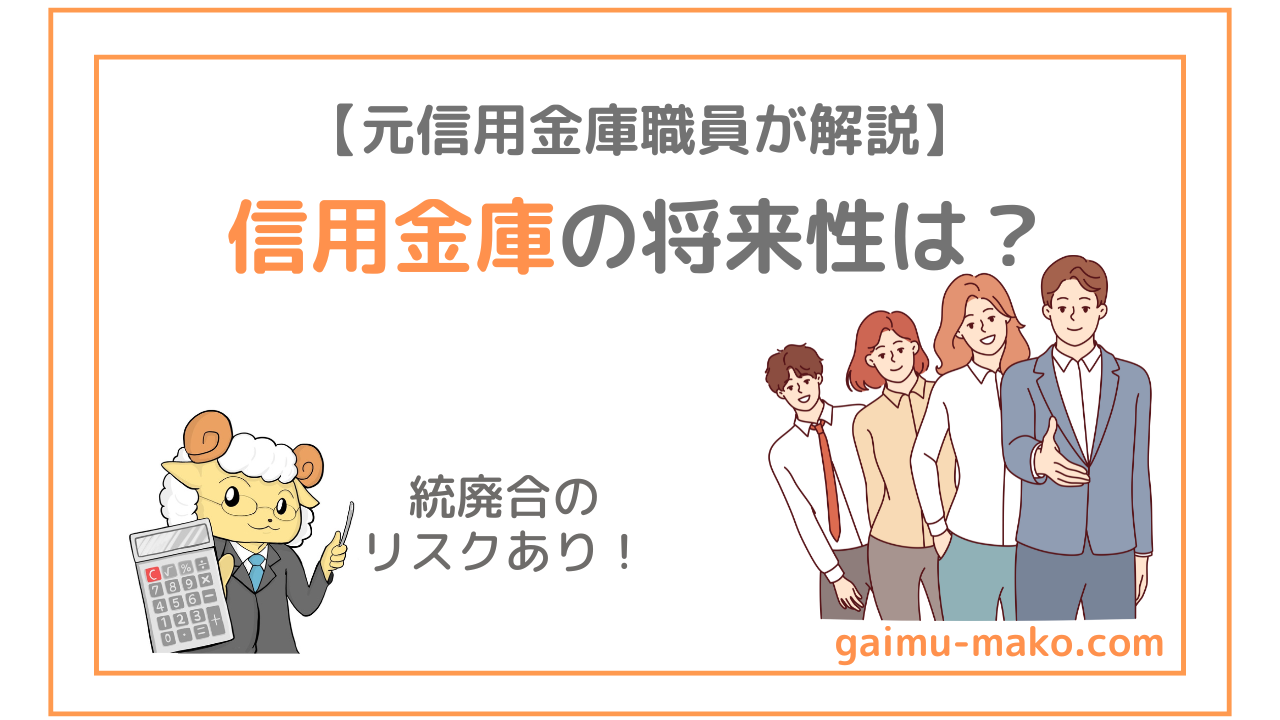
- 信用金庫に将来性はある?
- 今後なくなるんじゃないの?
今後も信用金庫は残り続けるでしょう。銀行がカバーしきれない中小企業や高齢者を支える存在が必要です。
ただ、残れるのは一部の信用金庫のみ。実際、全国の信用金庫の数は267(2015年3月末)でしたが、254(2025年3月末)まで減少しています。
勤務先の信用金庫の経営状況が厳しい状況であれば、資格取得・転職活動などに励みましょう。

私は将来性が見込めない信用金庫にいたため、転職しました。年収アップし、営業ノルマで詰められない会社に勤務しています。
控えめに言って、信用金庫を辞めてよかったです。
本記事では、元信用金庫職員の視点から、信用金庫が将来性を持つ理由と懸念される理由、今後の動向、そして職員が取るべき選択肢までを解説します。
【3選】信用金庫の将来性がないと言われる理由
信用金庫に将来性がないと言われます。ネット銀行の台頭や地方の人口減少などと収益環境が厳しくなっていることが理由でしょう。
客観的なデータを見ても信用金庫の数が減っているのは明らかです。
以下では、信用金庫に将来性がないと言われる主な理由を解説します。
信用金庫の数が減少している
信金中央金庫のデータによると、信用金庫の数は減少傾向にあります。

信金中央金庫は信用金庫の中枢的な組織です。
信用金庫の数が減少する理由として、以下のようなものが挙げられます。
- 人口減少による地方経済の縮小
- 低金利政策による収益性の低下
- 経営基盤の強化を目的とした合併戦略
特に地方の小規模信用金庫では、単独での経営継続が難しい状況のようで近隣の信用金庫との合併を選択するケースが増えています。
私が調査したところ信用金庫の数は267(2015年3月末)でしたが、254(2025年3月末)まで減少しています。

2024年から2025年の間は信用金庫の統廃合はありませんでしたが、長期的に見れば緩やかに減少しつつあるようです。
職員数が減少している
信用金庫では全体的に職員数が減少しています。
全国 254 信用金庫の常勤役職員数は、長期的に減少傾向にあり、2022年度末、23年度 末と2年連続で10万人を下回り、23年度末には約9.7万人となった。1994 年度末には16万人を超えていたので、この30年弱で約4割減少したことになる。
働く人が減る業界に将来性は見込めないでしょう。
上記はあくまで全信用金庫合計の職員数の推移です。私の前職の地方の信用金庫では、30年で約4割ではなく10年で約4割減少していました。

職員数の多い世代の定年退職による影響もあります。しかし、10年で4割の減少は異常でした。
競合の台頭で競争が激化

信用金庫の競合ってどこだろ?

個人顧客はネット銀行、法人顧客は地方銀行との競合が激しいですね。
ネット銀行の台頭により信用金庫は厳しい状況にさらされています。手数料と利便性において、ネット銀行をより高い付加価値を出すことは困難です。
- 物理的な店舗運営コストがなく、手数料や金利で競争力がある
- 24時間365日サービスを提供できる利便性
また、法人顧客は地方銀行との競合になることが多いです。地方銀行の方が低金利で優位です。
上記のような厳しい外部環境の中、法人顧客への事業支援、高齢者向けのきめ細かいサービスにより信用金庫の独自性を出さなくてはいけません。
難しい舵取りを迫られており、将来性は厳しいと言えるでしょう。
信用金庫がなくなるって本当?元職員が解説
ネット上には「信用金庫がなくなる」という声があるようです。ですが、信用金庫が完全になくなる状況は考えづらいです。

信用金庫がなくなるは言い過ぎです。
中小企業への経営支援や高齢者向けの金融サービスの提供など、他の金融機関では補えないサービスがあります。信用金庫がなくなる可能性は低いでしょう。
ですが、収益基盤の安定した信用金庫とそうでない信用金庫の2極化が一層加速すると考えられます。
今働いている信用金庫がどちらの信用金庫か見極める必要があります。
「信用金庫がなくなる」は言い過ぎ
信用金庫がなくなる可能性は低いです。
たしかにネット銀行などとの競争激化、人口減少による収益の悪化は避けられません。
しかし、高齢顧客への定期的な訪問、中小企業の支援など銀行では補いきれないサービスを提供することで生き残る術はあります。

銀行があえて手をださないサービスで収益を確保をできます。
地域に根差した信用金庫は今後も社会から必要とされるでしょう。
倒産のリスクは低いが規模縮小や統廃合される見込み
信用金庫は万が一経営不振に陥った際でも公的資金の注入が見込まれるなど、倒産するリスクは低いと言えます。
しかし、経営環境の厳しさから規模縮小や統廃合が進む可能性は高いでしょう。特に経営基盤の弱い地方の信用金庫では、単独での存続が難しくなり、より大きな信用金庫との統合によって効率化を図る動きが今後も続くと予想されます。
信用金庫の役割と現状
信用金庫は、地域の中小企業や個人に寄り添った金融サービスの提供を使命とする協同組織金融機関です。
銀行が全国規模で収益を追求するのに対し、信用金庫は営業エリアが限定され、地元の経済発展を第一に考えています。
地域密着型の経営方針が、信用金庫の最大の特徴です。
地域経済への貢献が役割
信用金庫の最も重要な役割は、地域経済への貢献です。
具体的には、地元の中小企業への融資や創業支援、個人の資産形成サポート、さらに地域イベントへの協賛など多岐にわたります。
信用金庫は地域社会の持続的発展に寄与しており、特に地方においては地域経済のインフラとしての役割を果たしています。
銀行とは違うアプローチで地域貢献することで、厳しい競争も生き残り続けられるでしょう。
職員の待遇は働きやすく年功序列
信用金庫の職員の待遇については、一般的に「働きやすさ」と「年功序列」が特徴です。
地方に根差した金融機関として、残業時間が比較的少なく、休暇取得もしやすい環境が整っていることが多いです。
給与体系は年功序列が基本となっており、勤続年数に応じて安定した昇給が期待できます。ただし、銀行と比較すると給与水準はやや低めの傾向があります。
信用金庫の今後の動向予測
信用金庫の収益環境は、厳しい状況が予測されます。
デジタル化の進展に伴い、オンラインサービスの拡充は避けられない流れとなるでしょう。
一方で、信用金庫ならではの対面でのきめ細かなサービスという強みを活かした差別化も進むと考えられます。
地域によって状況は異なりますが、以下にその具体的な展望をお伝えします。
事業性融資の伸びがカギを握る
信用金庫の今後の持続可能性を考える上で、事業性融資の伸びが重要な指標となります。
地域の中小企業に対する融資は信用金庫の本来の使命であり、この分野での実績が経営基盤を支えるカギとなるでしょう。
低金利環境が続く中で、融資の量だけでなく収益性の高い融資先の開拓も重要になってきています。
地方の信用金庫は統廃合が進む可能性高い
人口減少や高齢化が進む地方では、信用金庫の経営環境はさらに厳しさを増しています。
小規模な信用金庫では、デジタル投資や人材確保のコストを単独で負担することが難しくなっており、経営基盤の強化を目的とした統廃合が今後も加速する可能性が高いでしょう。
特に預金量が1兆円未満の中小規模の信用金庫では、生き残りをかけた再編の動きが活発化すると予想されます。
都市部の信用金庫は安泰
都市部の信用金庫はメリットを活かし、安定した経営基盤を維持できると考えられます。
大都市圏では企業数も多く、融資先の確保や個人顧客の獲得がしやすいため、地方の信用金庫と比較して経営状況は良好です。
また、規模の大きな信用金庫では、デジタル化投資やサービス多様化にも対応できるだけの資金力があります。
統廃合された側の職員の末路
統廃合が行われた場合、被合併側の信用金庫職員はさまざまな状況に直面します。
一般的には以下のようなケースが考えられます。
- 配置転換される可能性がある
- リストラ対象となる恐れがある
- 今後出世が厳しい可能性がある
- 被合併側の職員は給与体系が異なる恐れがある
統廃合後は、特に重複する部署や管理職ポストの削減が行われるため、中間管理職が最も影響を受けやすい傾向があります。
また、システム統合により業務フローが変わることで、長年慣れ親しんだ仕事のやり方が大きく変わることへの適応も求められます。
信用金庫職員が取るべき選択肢
信用金庫職員が将来に備えてとるべき選択肢はいくつかあります。業界の変化に対応し、自身のキャリアを守るためには、以下のような具体的なアクションが考えられます。
資格取得で専門性アップ
信用金庫職員として、また金融業界全体で通用するスキルを磨くために、資格取得は非常に効果的な手段です。具体的に役立つ資格としては以下が挙げられます。
- FP(ファイナンシャルプランナー)資格
- 証券外務員資格
- 中小企業診断士
- 宅地建物取引士
これらの資格は信用金庫内でのキャリアアップだけでなく、万が一の統廃合や転職の際にも強力な武器となります。
特に中小企業診断士は信用金庫の本来の役割である地域企業支援に直結するため、高く評価される傾向があります。
副業でスキルアップ
近年は副業を容認する金融機関も増えてきており、本業と両立しながら新しいスキルを身につける選択肢も考えられます。
- FPとしての個人相談業務
- Webライティング
- セミナー講師
- 税務・会計サポート
副業を通じて得られるスキルや人脈は、本業にも良い影響をもたらすだけでなく、将来独立や転職を考える際の足がかりにもなります。
ただし、副業を行う際は所属する信用金庫の就業規則を確認し、コンプライアンス上の問題がないよう注意が必要です。
金融業界やコンサル業界への転職で年収アップ
信用金庫で培った経験やスキルは、他の金融機関やコンサルティング会社でも十分に活かせます。
- メガバンク
- 地方銀行
- コンサル業界
- 地方公務員
- 事業会社の経理職
転職を成功させるためには、日頃から業界動向にアンテナを張り、自身のスキルを客観的に評価し、足りない部分を補う努力が必要です。
また、信用金庫時代の人脈を大切にし、転職後もビジネスチャンスにつなげられるよう関係性を維持することも重要です。
信用金庫はすぐにはなくならないが統廃合のリスクあり
信用金庫は地域金融機関として重要な役割を担っており、すぐに消滅するという心配はありません。
しかし、経営環境の変化や人口減少などの影響から、今後も統廃合が進む可能性は高いと言えます。
信用金庫が存続し続ける理由としては以下が挙げられます。
- 地域密着型の金融サービスへのニーズは依然として存在する
- 中小企業や個人事業主の資金調達先として重要な役割を果たしている
- 協同組織金融機関としての法的位置づけがある
- 地域経済の活性化に不可欠な存在として行政からも支援がある
一方で、以下の理由から統廃合のリスクは今後も続くと予想されます。
- 人口減少による取引先の減少
- デジタル化投資の負担増大
- 低金利環境の長期化による収益性の低下
- ネット銀行との競争激化
特に経営基盤が弱い小規模信用金庫や、過疎化が進む地域の信用金庫は、将来的に近隣の信用金庫との合併を選択せざるを得ないケースが増えるでしょう。
このような環境変化の中で、信用金庫が生き残るためには、デジタル化への適応、専門性の高いコンサルティング機能の強化、地域に根差した独自のサービス開発などが重要となります。