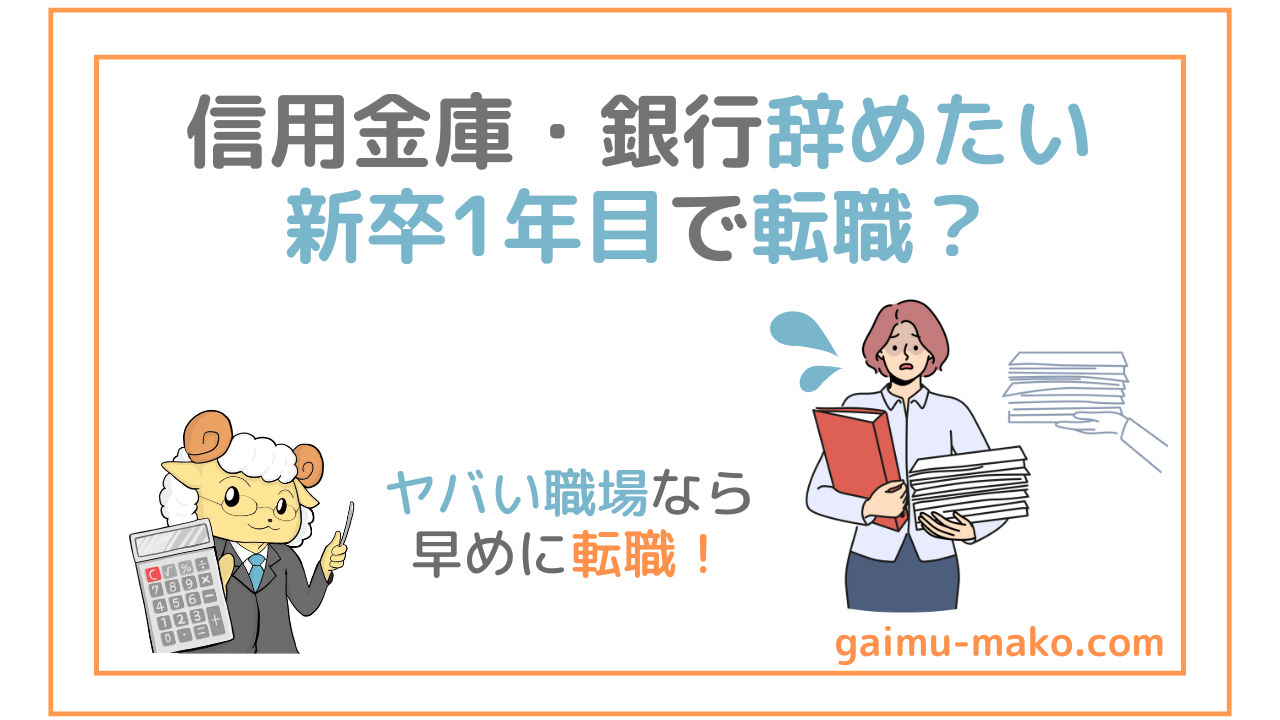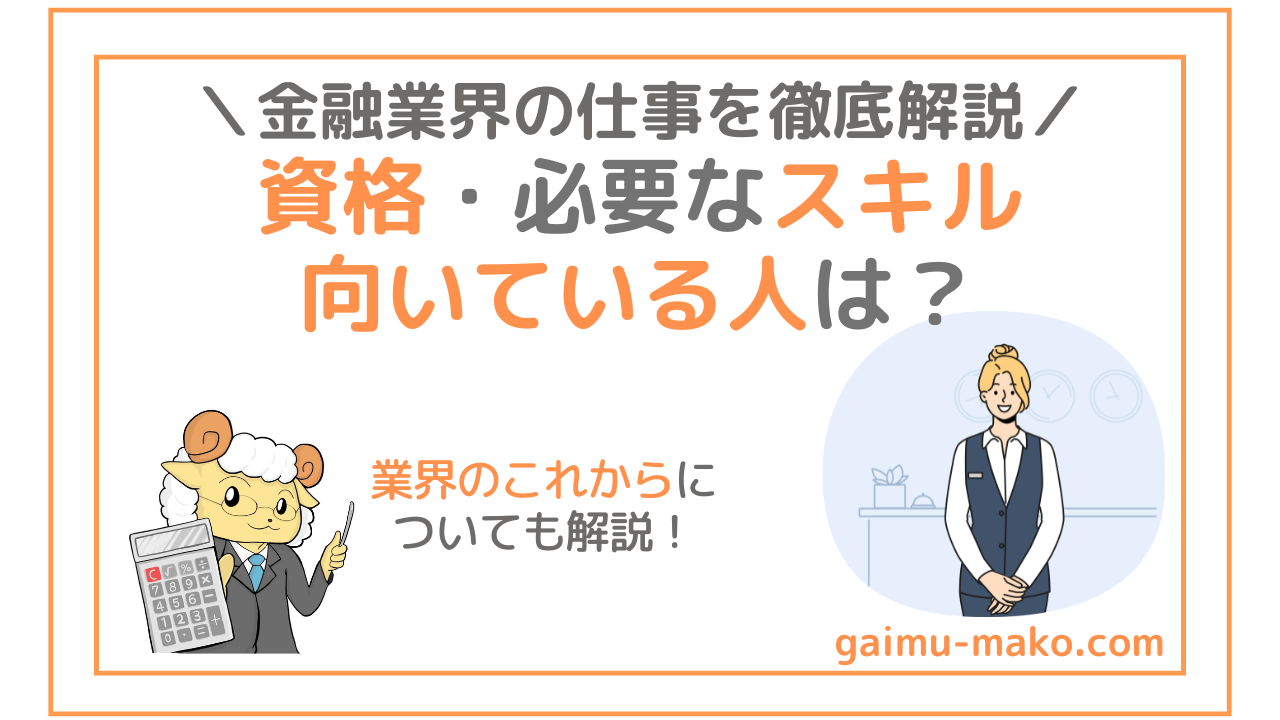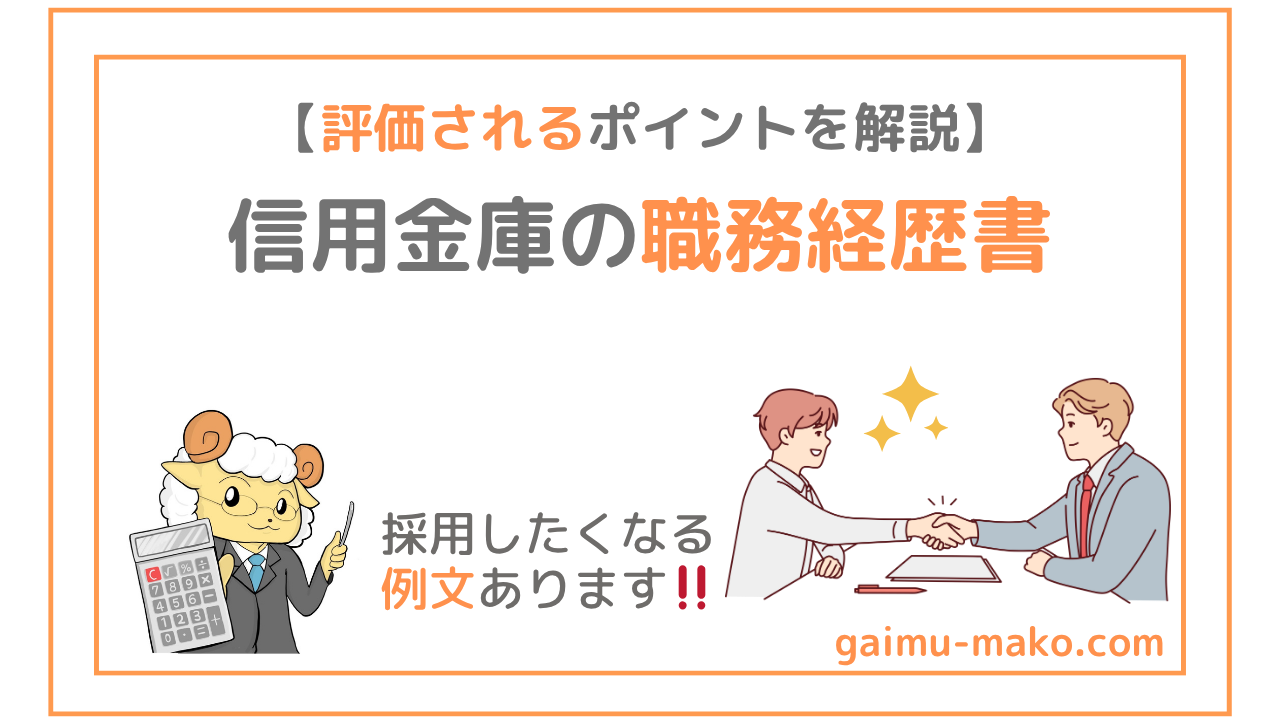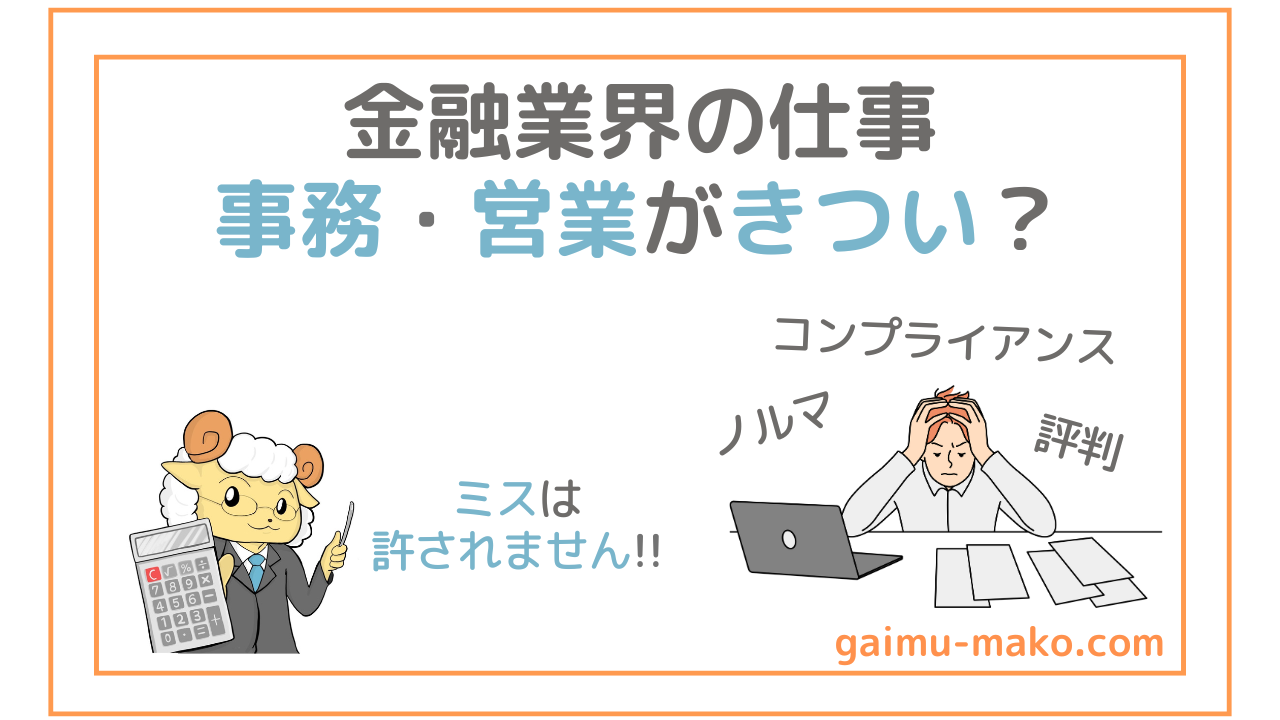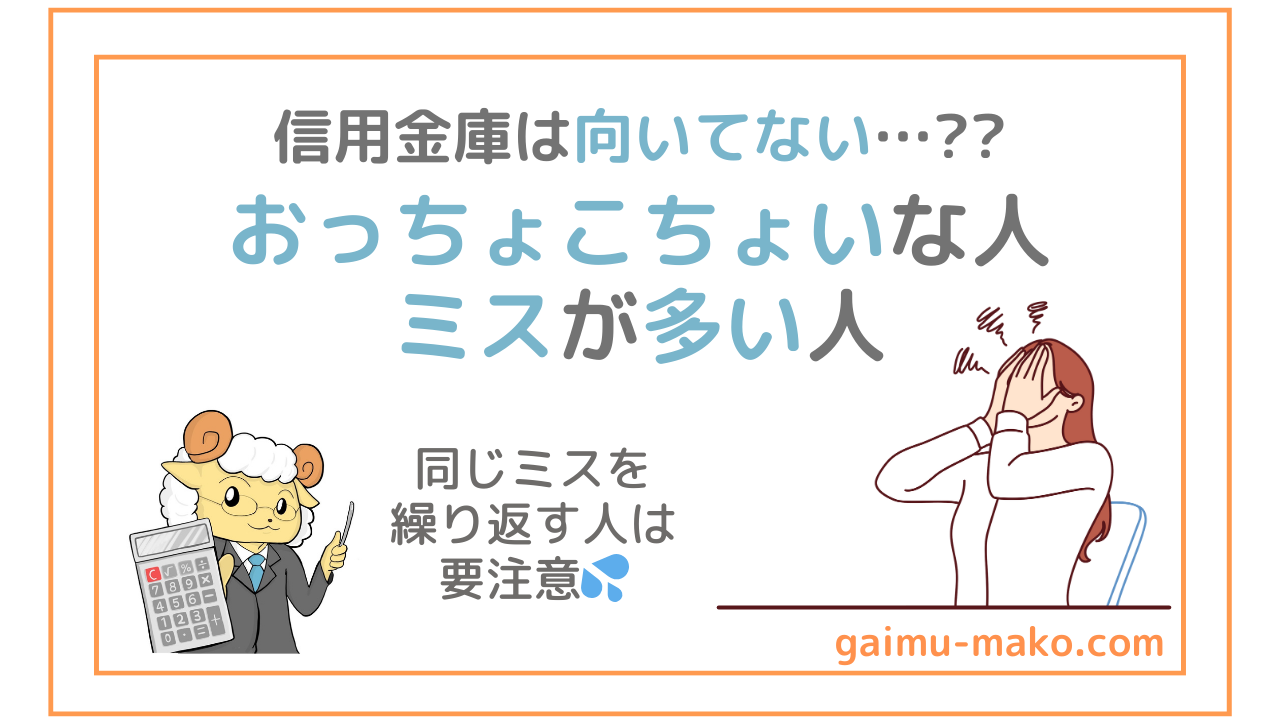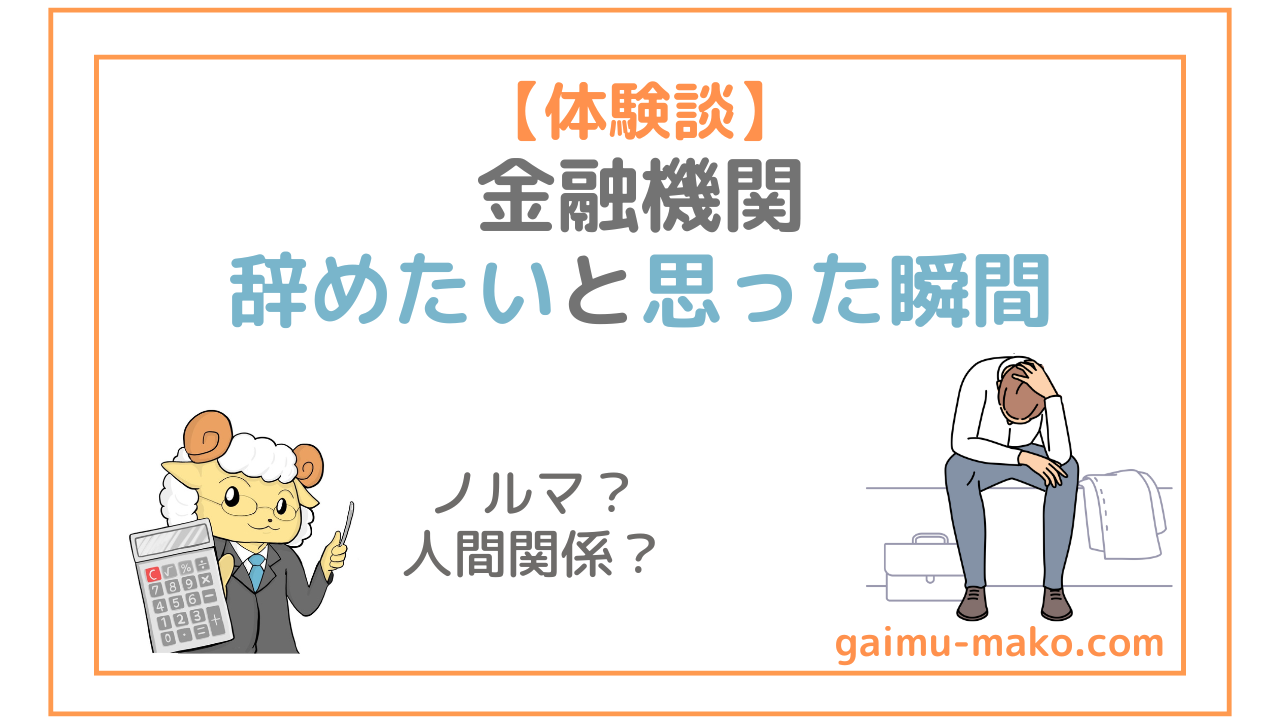営業職なのに社内でずっと仕事するのはダメ社員?なぜ営業に行かないのかと詰められる理由を解説
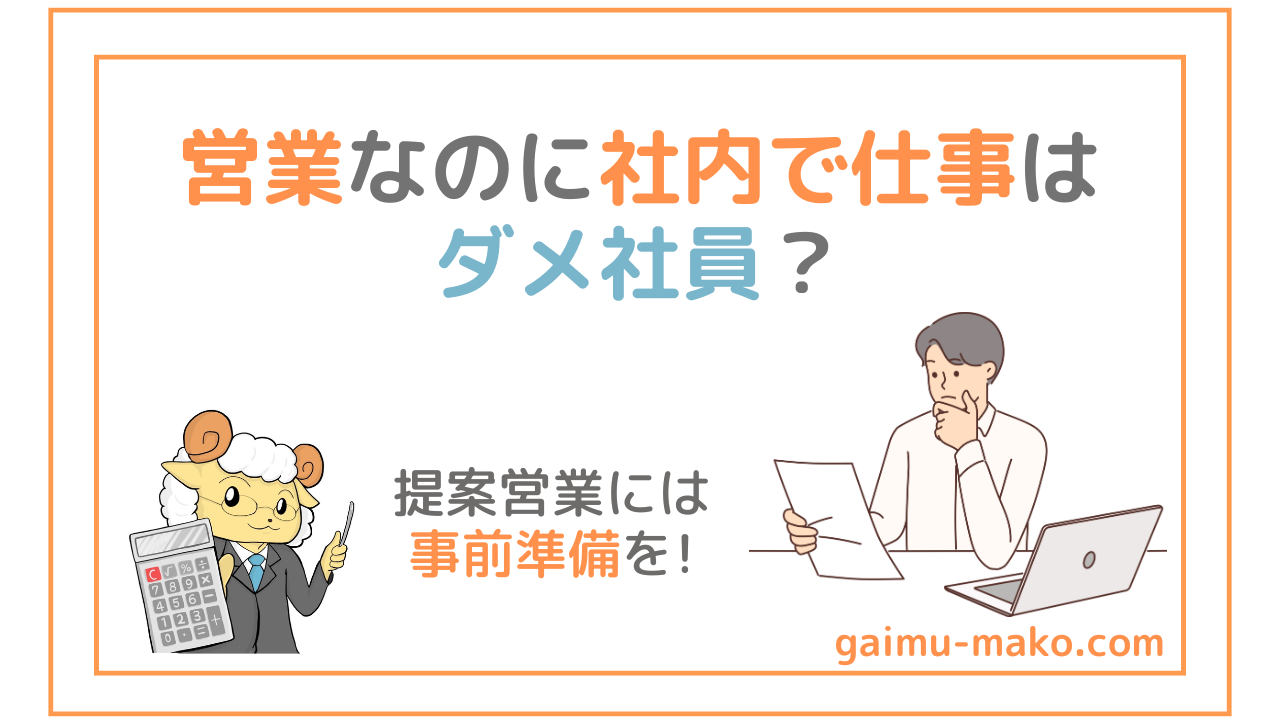
- 「営業ならもっと訪問してこい」と言われた
- 社内の書類仕事をしているのに・・・
- 根性論で「とにかく回れ」と指示される
「営業なんだから、1件でも多くの顧客先を回れ」
このように上司から指示をされたことはありませんか?
私は信用金庫で営業をしていた際、毎日のように訪問件数を増やすように指示されていました。
しかし、ある時から「訪問件数を増やす営業では、何も顧客に価値を提供できていないのではないか?」と思いはじめます。そして、顧客への提案書作成に時間を注ぐように。
ところが、上司は私の行動が気に食わなかった様子。「もっと営訪問件数を増やすように」と指示されます。ですが、訪問件数を増やすと、顧客1人にかける時間が減ります。
当時の私は上司の指示を無視して、顧客にとって価値ある提案をするため行動しました。

お客様から感謝される提案ができたため、個人的には満足しています。
しかし、上司からは冷たい態度を取られ、肩身の狭い思いをしました。自業自得と言われればそれまでですが。
- 営業がいるのは社内で必要な業務があるから
- 量よりも事前準備に時間をかける提案営業が重要
- 上司に評価されないのであれば転職を検討するという手も

私は転職エージェントを利用して他業界への営業職へ転職しました。
職場の悩みなど、まずは気軽に転職エージェントに相談してみましょう。
【実体験】10時過ぎて社内にいたら怒られた営業
私が以前勤めていた信用金庫では、朝9時までには外出しなければいけない風潮がありました。

営業は基本的に8:45の朝礼後には外出。
外出があまりに遅いと上司から詰められることもしばしば。
担当地域にもよりますが、1日25軒以上は訪問ノルマがありました。25軒訪問しようと思えば、1件あたりにかける時間が少なすぎて満足な営業活動ができません。

売上集金、振込手続きや公共料金の支払いなどの手続きもあり、移動時間も含めると提案書の作成や事務作業がなくなってしまいます。
1日25軒の営業ノルマができない
私の前職の金融機関では、1日25軒の訪問ノルマが課せられていました。ここで言う軒とは、世帯や会社で1先に営業したと換算するという意味です。
25軒への訪問を多いと感じるか、少ないと感じるかは業界や顧客層によっても異なると思います。
ただ、私は多すぎると感じました。1日25軒営業しないといけない場合、1日8時間とすると顧客1人に注げる時間は約20分です。これでは時間が足りません。
個人なら顧客の世帯情報やライフプラン、資産状況を踏まえて提案する預かり資産商品を提案する必要があります。
法人ならば、決算書などの財務状況や資金繰りを把握し、既存融資の巻き直しや新規設備の需要の聞き取りが必要。
移動時間の他に提案資料を作成する、稟議申請に必要な資料を作成する、合議するなどの時間を含めると毎日25軒営業するのは至難の業です。
実際に1日25軒営業をコンスタントに営業できている人を見たことがありません。
上記の内容を上司に説明しました。しかし、どうやら理解できないようです。
「今までは既存先の巻き直しで良かったが、これからは新規先を開拓しないと先細る一方になってしまう。とにかく営業するように」と、ずっと主張されます。
10時に会社にいたら怒られる
営業は朝から外回りに出て、お客様の都合の良い時間に訪問する必要があるという考えが根強くあります。
そのため、午前10時になっても社内にいると、上司から「なぜまだ会社にいるんだ?」と叱責されることがありました。
しかし、この考え方には問題があります。
顧客への提案資料の作成や、データ分析、戦略立案など、社内での準備作業も営業活動の重要な一部です。また、お客様によっては午後からの方が都合が良い場合もあり、必ずしも朝一番からの訪問が最適とは限りません。
さらに、デジタル化が進んだ現代では、オンラインミーティングや電話での商談など、必ずしも対面でなくても効果的な営業活動が可能になっています。
営業職は外出が基本?営業スタイルの変化
営業職というと、多くの人は顧客との面談や外回りを中心とした仕事をイメージするでしょう。
営業といえば、毎日取引先を訪問し、商談を重ねながら信頼関係を築いていくという営業スタイルが定着しています。
ただし、近年は営業スタイルが大きく変化しており、特に金融営業では顧客訪問前の情報収集や事前準備が欠かせなくなっています。
顧客のニーズや市場動向を深く理解し、的確な提案を行うために、データ分析やマーケット調査、商品知識の習得など、デスクワークの重要性が増しているのです。
「なぜ社内にいるのか?」と上司が感じる理由
営業職が社内で過ごしている時間が長いことに違和感を感じる上司や内勤の社員がいるようです。
高度経済成長期の金融営業は、顧客との面談数が全て。とにかく人と会う。預金や融資をしてもらうだけで、儲かった。そんな時代もあったようです。
こうした価値観を持つ上司にとって、社内にずっといる営業担当には「なぜもっと顧客と面談しないんだ?」と疑問が生まれやすいのかもしれません。
特に、外出せずに営業活動をしていると、商談スキルや顧客との関係構築能力の低下を心配される傾向があります。
また、外出しない営業職は、具体的な業務内容や活動状況が見えにくいため、生産性や成果が不透明だと感じられることも少なくありません。
デスクワークが中心となる営業スタイルでは、どのような価値を生み出しているのか、どのように顧客との関係を維持・強化しているのかが、周囲から見えづらいという課題があります。
このような不安や懸念を解消するためには、営業活動の内容や成果を具体的に可視化し、日々の活動報告や進捗確認をこまめに行うことが重要です。また、社内での準備作業が最終的にどのような成果につながっているのかを、数値やデータを用いて示すことも効果的です。
社内業務の重要性と結果を出す方法
社内業務は営業活動において重要な役割を果たしています。以下に、社内業務の重要性と結果を出すための方法を説明します。
データ分析と戦略立案
顧客データの分析、市場調査、競合分析などを通じて、効果的な営業戦略を立案することができます。これにより、訪問先の優先順位付けや、より効率的な営業活動が可能になります。
提案資料の質向上
社内での十分な準備時間を確保することで、より質の高い提案資料を作成できます。顧客のニーズに合わせたカスタマイズされた提案は、成約率の向上につながります。
社内連携の強化
商品開発部門や管理部門との密な連携により、顧客ニーズに合った製品やサービスの提案が可能になります。また、スムーズな案件処理にもつながります。
デジタルツールの活用
CRMシステムやオンライン会議ツールを効果的に活用することで、対面営業と同等以上の成果を上げることができます。これらのツールは、顧客との関係維持にも役立ちます。
時間の効率的な活用
移動時間を削減し、その時間を戦略立案や提案準備に充てることで、より効果的な営業活動が可能になります。また、より多くの顧客とコンタクトを取ることができます。
社内業務に対する不安を解消するために
上司や同僚が社内営業に対して不安を感じている場合、その不安を解消する方法を考えることも大切です。
定期的な活動報告の実施
日々の活動内容や成果を具体的に報告することで、社内業務の重要性と効果を上司や同僚に理解してもらうことができます。数値データや具体的な成功事例を示すことが効果的です。
成果の可視化
社内業務が最終的な営業成果にどのようにつながっているかを明確に示すことが重要です。例えば、データ分析による商談成約率の向上や、効率的な時間活用による顧客接点の増加などを具体的に示します。
コミュニケーションの強化
上司や同僚との定期的なミーティングを設け、現在の取り組みや課題、今後の計画について共有します。オープンなコミュニケーションを通じて、相互理解を深めることができます。
ハイブリッド型営業の実践
社内業務と外回り営業をバランスよく組み合わせることで、それぞれの利点を最大限に活かすことができます。状況に応じて柔軟に営業スタイルを変更する姿勢も重要です。
目標設定と進捗管理
明確な目標を設定し、その達成に向けた進捗を定期的に確認することで、社内業務の必要性と効果を示すことができます。また、必要に応じて目標や活動内容の見直しを行うことも大切です。
まとめ
営業職が社内で過ごす時間が増えていることは、現代のビジネス環境における自然な変化です。
データ分析、戦略立案、提案資料の作成など、社内業務は効果的な営業活動に不可欠な要素となっています。
重要なのは、以下の点に注意を払うことです:
- 社内業務の成果を可視化し、定期的に報告する
- デジタルツールを効果的に活用して生産性を向上させる
- 上司や同僚との良好なコミュニケーションを維持する
- 明確な目標設定と進捗管理を行う
社内業務と外回り営業を適切にバランスを取ることで、より効果的な営業活動が実現できます。重要なのは、最終的な成果を出すことであり、その過程での時間の使い方は、状況や目的に応じて柔軟に対応することが求められます。
.png)